筋力トレーニングに取り組む多くの人が直面する悩みの一つが、お酒との付き合い方です。体づくりに励みながらも、仕事や付き合いでお酒を楽しみたいというのが、現代人の率直な気持ちでしょう。
筋トレとお酒の関係について、結論から申し上げれば「適度な飲酒であれば、トレーニング効果を大きく損なうことはありません」。ただし、その「適度」の範囲を知り、正しい飲み方を実践することが重要です。
- 筋タンパク質合成への作用
- ホルモンバランスへの影響
- 回復過程への関与
- 水分代謝への効果
一方で、適量のお酒にはストレス解消やコミュニケーションの促進といったメリットもあります。大切なのは、体づくりの目標と生活の質のバランスを取ることです。
この記事では、最新の研究結果に基づき、筋トレとお酒の両立について徹底的に解説します。トレーニング効果を最大限に引き出しながら、どのようにお酒と付き合っていくべきか、その具体的な方法をご紹介していきます。
適切な知識を身につけることで、健康的な体づくりと適度な飲酒を無理なく両立させることが可能になります。あなたのライフスタイルに合った、ベストな選択ができるようになるはずです。
飲酒・アルコールのメリット・デメリット【一般論】
適度な飲酒は生活に彩りを添え、心身のリフレッシュをもたらす一方で、過度な飲酒は健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。適量と過剰の境界を理解し、自身の体質に合った飲酒習慣を確立することが重要です。

お酒の主なメリット
飲酒には以下のような積極的な効果が期待できます。
- 心身への好影響
-
- ストレス解消とリラックス効果で心身をリフレッシュ
- 食欲増進により、食事をより楽しく豊かに
- 赤ワインのポリフェノールには、適量摂取で心血管系への良好な影響も
- 社会面での効果
-
- 円滑なコミュニケーションのサポート
- 社交の場での関係構築の促進
- 気分転換による生活の質の向上
お酒がもたらす健康への影響
過度な飲酒は、以下のような健康上の問題を引き起こす可能性があります。
- 体組成への影響
-
- アルコール自体が高カロリー(1g = 7kcal)
- 飲酒に伴う過食や糖分摂取による体重増加
- 水分代謝の乱れによる一時的な体重変動
- 栄養と代謝への干渉
-
- ビタミンB群やミネラルの吸収阻害
- タンパク質合成の低下による筋肉への悪影響
- 代謝機能の低下と栄養バランスの乱れ
- 睡眠と回復への支障
-
- 睡眠の質の低下(特に深睡眠の減少)
- 成長ホルモン分泌の抑制
- 疲労回復の遅延と日中のパフォーマンス低下
- 肝機能への負荷
-
- 肝臓での代謝負荷の増大
- 継続的な過剰摂取による肝機能低下のリスク
- タンパク質合成能力の低下による全身への影響
お酒は適量であれば生活を豊かにする一方で、過度な摂取は健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。自身の体質や目標、体調を考慮しながら、適切な飲酒量とタイミングを見極めることが重要です。
次節では、筋トレと飲酒の関係について、より具体的に解説していきます。
筋トレと飲酒の関係:最新の研究結果
筋トレと適度な飲酒の両立について、多くのトレーニー達が関心を持っています。最新の研究結果を基に、アルコールが筋トレに与える影響とそのメカニズムについて詳しく解説していきましょう。

適度な飲酒と筋トレの関係性
研究によると、適度な飲酒は筋トレへの悪影響が比較的軽微であることが明らかになっています。1日1〜2杯程度のアルコール摂取であれば、筋肉の成長を大きく妨げる可能性は低いとされています。
ただし重要な注意点として、トレーニング直後の飲酒は避けるべきです。なぜなら、この時期は筋肉の回復と成長が最も活発な時期であり、アルコールがこのプロセスを阻害する可能性があるためです。1
過度の飲酒による悪影響とそのメカニズム
過度の飲酒は、以下の経路で筋トレ効果を著しく低下させる可能性があります。
これらの研究結果から、適度な飲酒であれば筋トレとの両立は可能ですが、その量とタイミングには十分な注意が必要です。自身の体調や目標に合わせて、適切な飲酒量を設定することが重要です。また、定期的に体調をモニタリングし、必要に応じて飲酒量を調整することをおすすめします。
アルコール摂取の筋肉への影響
アルコールの摂取は、筋トレの効果に様々な影響を及ぼします。特に過度な飲酒は、筋肉の成長や回復に深刻な影響を与える可能性があります。

ホルモン系への影響と筋肉分解のリスク
アルコールは体内の重要なホルモンバランスを乱し、筋肉の分解(異化)を促進する可能性があります。主な影響は以下の2つのホルモン経路を通じて生じます。
- テストステロンの低下:アルコールは男性ホルモンの分泌を抑制し、筋肉の成長と維持に必要なテストステロンレベルを低下させます
- コルチゾールの増加:アルコールはストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促進し、これが筋タンパク質の分解を加速させる可能性があります
これらのホルモンバランスの乱れは、筋肉の合成抑制と分解促進の両面から、トレーニングの効果を減少させる可能性があります。特にトレーニング後の回復期に飲酒すると、この影響が顕著になることが研究で示されています。
さらに、アルコールはタンパク質合成を阻害する直接的な作用も持っています。これにより、トレーニングによる**筋肉の肥大(成長)**が妨げられる可能性があります。ただし、この影響は飲酒量に大きく依存し、適度な飲酒であれば深刻な影響は少ないとされています。
急性アルコール筋症(ミオパチー)について
急性アルコール筋症は、過度の飲酒によって引き起こされる深刻な筋肉障害です。10これは単なる筋肉痛とは異なり、医学的な対応が必要となる可能性がある状態です。
- 筋肉の急性障害:激しい筋肉痛や筋力低下
- 身体的変化:筋肉の腫れや異常な硬直
- 深刻な症状:褐色尿(ミオグロビン尿)の出現
- 発症時期:大量飲酒から数時間〜数日後
特に注意すべきは、この症状が筋繊維の部分的な壊死を引き起こす可能性があり、重症化すると生命に関わる横紋筋融解症に発展する危険性があることです。
日本人の遺伝的特徴とアルコールの影響
日本人を含むアジア人は、遺伝的な特徴によってアルコールの影響を受けやすい体質を持っています。これは主にアルコール代謝酵素の遺伝的変異に起因します。1112
- 少量の飲酒でも強い影響を受ける
- 二日酔いの症状が出やすい
- アルコールによる健康影響を受けやすい
このため、欧米のアルコール摂取基準をそのまま適用することは適切ではありません。個人の体質と遺伝的背景を考慮した、より控えめな飲酒量を設定する必要があります。
アルコールでテストステロンが減少する可能性
アルコールは男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌に重要な影響を与えます。その影響は飲酒パターンによって異なります。
- 短期的影響:大量飲酒直後は一時的な上昇の後、急激な低下
- 長期的影響:継続的な過剰飲酒による恒常的な低下
- 適度な飲酒:最小限の影響で、場合によってはわずかな増加も
筋トレの効果を最大化するためには、これらの影響を理解した上で、個人の体質や目標に合わせた適切な飲酒習慣を確立することが重要です。特に、トレーニング期間中は慎重な飲酒管理が求められます。
減量期と増量期における飲酒の影響の違い
筋トレを行う上で、減量期と増量期では飲酒が身体に与える影響が大きく異なります。それぞれの時期に合わせた適切な飲酒管理が、目標達成の鍵となります。

減量期の飲酒:注意点と対策
減量期は、体脂肪を減らしながら大切な筋肉を維持するという繊細な時期です。この時期の飲酒は、以下の理由から特に慎重な管理が必要となります。
- カロリー摂取の増加:アルコール自体が7kcal/gと高カロリー
- 代謝効率の低下:アルコールの分解が優先され、脂肪燃焼が抑制
- 食欲増進作用:飲酒後の過食リスクが上昇
- 水分保持の促進:一時的な体重増加と見た目の変化
しかし、完全な禁酒が現実的でない場合も多いため、以下の対策を実践することで、減量への悪影響を最小限に抑えることができます。
- 低カロリー蒸留酒の選択:ウイスキーやジンなどを、糖分の少ないミキサーで
- 飲酒頻度の制限:週1-2回までとし、1回あたり1-2杯まで
- 事前の食事管理:タンパク質を含む食事を摂取し、空腹での飲酒を回避
- おつまみの工夫:低脂肪高タンパクな食材を選択(刺身、蒸し鶏など)
- 翌日の運動管理:軽めの有酸素運動で代謝を促進
特に重要なのは、飲酒量の管理とタイミングです。トレーニングの2-3時間後は避け、できるだけ休養日に飲酒するよう心がけましょう。また、アルコールによる脱水を防ぐため、こまめな水分補給も欠かせません。
このような管理を実践することで、減量期でも時には適度な飲酒を楽しみながら、目標達成への道を進むことが可能となります。
増量期の飲酒:メリットとデメリット
増量期は、質の高い筋肉量の増加を目指す重要な時期です。この期間における飲酒の影響は、減量期とは異なる特徴を持ちます。
- カロリー補給の補助:アルコールの高カロリーが総摂取カロリーを増やすのに寄与
- ストレス管理:適度な飲酒による精神的リラックスがトレーニングの継続をサポート
- コミュニケーション促進:社交の機会を通じた精神的な充足感の獲得
しかし、増量期特有の注意点も存在します。過度な飲酒は以下のような悪影響をもたらす可能性があります。
- 筋タンパク質合成の低下:アルコールによる筋肉の成長・修復プロセスの阻害
- ホルモンバランスの乱れ:テストステロンや成長ホルモンの分泌抑制
- 栄養素の吸収阻害:特にビタミンB群やミネラルの吸収効率低下
- 筋肉の回復遅延:過剰な飲酒による回復プロセスの遅延
これらの影響を考慮しつつ、以下のような飲酒管理を実践することで、増量期でも適度な飲酒を楽しむことが可能です。
- 適切な飲酒量の設定:週2-3回までとし、1回あたり2-3杯を目安に
- 栄養補給のタイミング:飲酒後は良質なタンパク質と炭水化物を摂取
- トレーニングとの調整:トレーニング直後2-3時間は飲酒を避ける
- 翌日のケア:十分な水分補給と栄養バランスの取れた食事を心がける
増量期では、総摂取カロリーと栄養バランスが特に重要です。飲酒による空カロリーの摂取は、質の高い増量の妨げとなる可能性があることを忘れずに、自身の体調と目標に合わせて適切な飲酒管理を行いましょう。
筋トレと飲酒を両立させるための具体的な戦略
多くのトレーニー達が筋トレと飲酒の両立を望んでいます。ここでは、最新の研究知見に基づいて、筋トレの効果を最大限に引き出しながら、お酒を楽しむための具体的な戦略をご紹介します。

トレーニング直後の飲酒を避ける理由と対策
トレーニング直後の飲酒は、筋肉の回復と成長に重大な影響を及ぼす可能性があります。特に注意すべき影響として、以下の3つが挙げられます。
まず、筋タンパク質合成の阻害です。トレーニング後は筋タンパク質の合成が活発になる重要な時期ですが、アルコールはこのプロセスを著しく抑制してしまいます。この影響は、トレーニングの成果を最大限に引き出す機会を逃すことになりかねません。
次に、深刻な脱水のリスクです。トレーニングですでに失われた体内の水分に加えて、アルコールの利尿作用により、さらなる水分損失が起こります。これは筋肉の回復プロセスを遅らせるだけでなく、体調不良のリスクも高めます。
そして、栄養吸収の阻害です。トレーニング後の栄養補給は筋肉の回復と成長に不可欠ですが、アルコールは必要な栄養素の吸収を妨げ、回復に必要な栄養が十分に活用されない状態を引き起こします。
- トレーニング後は最低2-3時間の間隔を設ける
- プロテインとBCAAの摂取を飲酒前に済ませる
- 飲酒時は水分補給を徹底する(アルコール1杯につき水1杯が目安)
- アルコールの種類は糖質の少ない蒸留酒を選択する
これらの戦略を実践することで、筋トレの効果を維持しながら、適度な飲酒を楽しむことができます。ただし、これはあくまでも一般的な指針であり、個人の体質や目標に応じて調整することが重要です。
飲酒後のトレーニングへの影響と回復方法
飲酒翌日のトレーニングには特別な注意が必要です。アルコールの影響により、運動パフォーマンスの低下と怪我のリスクが著しく高まるためです。この影響は、飲酒量や個人の代謝能力によって異なりますが、一般的に以下のような問題が起こります。
まず、中枢神経系への影響が挙げられます。アルコールは脳の情報処理能力を低下させ、反応時間の遅延や動作の正確性の低下を引き起こします。これは特に、高重量のトレーニングや複雑な動作を必要とするエクササイズで危険となります。
また、前庭感覚器系への影響により、バランス感覚や空間認識能力が低下します。この状態でトレーニングを行うと、フォームが崩れやすく、怪我のリスクが高まります。
さらに、アルコールの利尿作用による脱水状態は、筋肉の機能低下や疲労の早期発現を引き起こす可能性があります。
- 休息と水分補給を優先する(特に飲酒後12時間は要注意)
- トレーニング強度を通常の60-70%程度に抑える
- ウォーミングアップの時間を増やす(通常の1.5倍程度)
- 高重量トレーニングは避ける(特に頭上運動や複雑な動作)
アルコールの種類別影響比較
全てのアルコール飲料が同じように筋トレに影響するわけではありません。飲み物の種類によって、その影響は大きく異なります。以下に、主なアルコール飲料の特徴と筋トレへの影響を詳しく解説します。
🥃 蒸留酒(ウイスキー、焼酎、ウォッカなど)は、筋トレとの両立を考える上で比較的理想的な選択肢です。その理由は、純アルコールあたりのカロリーが最も低く、余分な糖質も含まないためです。ただし、高アルコール濃度のため、適量を守ることが特に重要です。
🍷 ワイン、特に赤ワインには、ポリフェノールなどの抗酸化物質が含まれており、適度な摂取であれば筋肉の回復を助ける可能性があります。しかし、糖質含有量には注意が必要です。
🍺 ビールは、筋トレとの相性が最も悪い飲み物の一つと言えます。その理由として、高カロリー、高糖質であることに加え、ホップに含まれる植物性エストロゲンがテストステロン分泌に影響を与える可能性があります。
🍹 カクテルは、ミキサーの種類によってカロリーと糖質が大きく変動します。特に、ジュースやシロップを使用したカクテルは、想定以上のカロリー摂取につながりやすいため注意が必要です。
- 蒸留酒のソーダ割りを基本とする
- 糖質の多いミキサーは避ける
- 赤ワインは適量であれば許容範囲
- ビールは特別な場合のみに制限する
これらの知識を活用することで、筋トレの効果を維持しながら、賢く飲酒を楽しむことができます。ただし、どのような種類のお酒でも、適量を守ることが最も重要な原則となります。
筋トレ効果を失わない飲酒作法
筋トレと飲酒を両立させたい方のために、トレーニング効果を最大限に保ちながら飲酒を楽しむ方法をご紹介します。適切な飲酒作法を実践することで、筋トレへの悪影響を最小限に抑えることができます。

蒸留酒を選ぶ
体づくりを意識する方は、カロリーと糖質の摂取を抑えるため、ビールやワインよりも蒸留酒を優先的に選択することをおすすめします。ウイスキー、焼酎、ウォッカなどの蒸留酒は、同じアルコール量でもカロリーが約半分で、糖質もほとんど含まれていません。
- カロリーの高いジュースなどのミキサーは控えめに
- ソーダ割りでさっぱりと
- ロックや水割りで味わい深く
水分補給を意識する
アルコールには強い利尿作用があり、体内の水分を急速に失わせます。この脱水状態は筋タンパク質の合成を著しく阻害し、せっかくのトレーニング効果を減少させてしまう可能性があります。
- アルコール1杯につき水1杯の原則を守る
- 飲酒前に500ml程度の水を摂取する
- 就寝前にスポーツドリンクなどの電解質を補給する
これらの習慣により、水分バランスの維持と二日酔いの予防が可能になります。また、翌日のトレーニングのコンディションも改善されます。
おつまみは高タンパク・低脂肪を意識する
筋トレをする方の飲酒時のおつまみ選びは、栄養バランスとカロリーコントロールの観点から特に重要です。高脂肪・高カロリーのおつまみは、せっかくのトレーニング効果を相殺してしまう可能性があります。
- タンパク質が豊富な食材を中心に
- 低脂肪・低カロリーなものを優先
- 食物繊維を含む野菜類も取り入れる
- 乳製品:低脂肪チーズ、ギリシャヨーグルト
- 魚介類:刺身、カルパッチョ、焼き魚
- 鶏肉:ささみ、むね肉のたたき、塩焼き鳥
- 豆類:枝豆、蒸し大豆
- サラダ・野菜:生野菜、グリル野菜
アルコールの種類を賢く選ぶ
ビールはホップに含まれる植物性エストロゲンにより、テストステロンの分泌を抑制する可能性があります。また、糖質とカロリーが比較的高いため、体づくりの観点からは注意が必要です。
- 赤ワイン:適量であれば抗酸化作用も期待できる
- 蒸留酒:カロリーと糖質を抑えられる
- 糖質オフビール:通常のビールの1/3以下の糖質
適量を心がける(できる人は)
厚生労働省の指針による純アルコール20gという基準は、筋トレをする方にとっても参考になる目安です。ただし、これは一般的な基準であり、トレーニングの強度や頻度、個人の体質によって調整が必要です。
- ビール中瓶:1本(500ml)
- 日本酒:1合(180ml)
- 焼酎:0.5合(90ml)
- ワイン:2杯(240ml)
- ウイスキー:ダブル1杯(60ml)
重要なのは、この量を絶対的な基準とせず、自身の体調や翌日のトレーニングへの影響を観察しながら、個人に合った適量を見つけることです。適切な飲酒習慣を確立することで、筋トレの効果を維持しながら、お酒を楽しむことが可能になります。
筋トレ効果を最大化するための飲酒ルール
筋トレの効果を最大限に引き出しながら、お酒を楽しむためには、適切な飲酒管理が重要です。科学的な根拠に基づいた具体的なガイドラインを紹介します。

週当たりの飲酒回数と量の目安
アルコールは筋タンパク質合成に影響を与えるため、適切な飲酒量の管理が重要です。研究によると、筋力トレーニングを行う人の場合、以下の基準が推奨されています。
- 週2-3回までの適度な頻度を維持する
- 1回あたりの純アルコール量は20-30g以下に抑える
- トレーニングの質を優先し、体調に応じて調整する
- 休養日に飲酒を計画する
- ビール中瓶1本(500ml)が適量の上限
- 日本酒1合(180ml)程度
- 焼酎0.5合(90ml)まで
- ワイン2杯(240ml)を超えない
これらの量を守ることで、筋肉の成長と回復を阻害することなく、お酒を楽しむことができます。特に、日本人の遺伝的特性を考慮すると、欧米の基準よりも控えめな量設定が望ましいでしょう。
重要なのは、これらは一般的な目安であり、個人の体質や体格、アルコール耐性によって適量は異なるということです。自身の体調や翌日のトレーニングへの影響を観察しながら、最適な飲酒量を見つけていくことが大切です。
飲酒のタイミングとトレーニングスケジュールの調整
筋トレと飲酒を両立させる上で、飲酒のタイミングは極めて重要です。研究によると、アルコールが筋タンパク質合成に与える影響は、摂取するタイミングによって大きく異なることがわかっています。
- トレーニング直後2-3時間は避ける(筋タンパク質合成が最も活発な時期)
- 休養日に飲酒を計画する(トレーニングへの直接的な影響を最小化)
- 深夜の飲酒を控える(質の高い睡眠の確保が重要)
- 翌日にハードなトレーニングが予定されている場合は避ける
深酒をした翌日のトレーニングでは、怪我のリスクが高まり、パフォーマンスの低下も避けられません。そのような場合は、軽めのカーディオや低強度のウェイトトレーニングに切り替えることで、リスクを最小限に抑えることができます。
飲酒後の回復を促進する栄養戦略
飲酒後の適切な栄養補給とリカバリーケアは、筋トレ効果を維持する上で決定的に重要です。アルコールによる悪影響を最小限に抑えるため、以下の点に注意を払いましょう。
- 水分と電解質の補給:アルコール1杯につき水1杯を目安に
- 質の高いタンパク質の摂取:飲酒前後に20-30gを目標に
- ビタミン・ミネラルの補充:特にB群ビタミンと亜鉛
- 睡眠の質の確保:通常より30-60分長めの睡眠時間を確保
- 軽いカーディオ運動で血行を促進
- ストレッチで筋肉の緊張をほぐす
- 栄養バランスの良い食事を心がける
- 十分な水分補給を継続する
これらの戦略を実践することで、飲酒による悪影響を最小限に抑えながら、筋トレの効果を維持することが可能です。ただし、これらは一般的なガイドラインであり、個人の体質や目標に応じて適切に調整することが重要です。定期的に自身の体調や進捗を評価し、必要に応じて方針を見直していきましょう。
筋肉のために禁酒するケース
筋トレをする人の多くにとって、適度な飲酒は問題ありませんが、特定の状況では完全な禁酒が推奨されます。筋肉の発達やパフォーマンスを最大限に引き出すため、以下のような場合は禁酒を考慮する必要があります。

プロアスリートの場合
プロアスリートには最高のパフォーマンスが求められます。そのため、飲酒が与える影響をより慎重に考える必要があります。アルコールは筋肉の回復や認知機能に影響を与え、競技力の低下を招く可能性があるためです。
- 競技シーズン:重要な試合や大会の前後2週間は、完全な禁酒が推奨されます。この期間のアルコール摂取は、反応速度や持久力に悪影響を与える可能性があります。
- リハビリ期間:怪我からの回復中は、アルコールが治癒プロセスを遅らせる可能性があります。特に、抗炎症作用を妨げたり、組織の修復を遅らせたりする可能性があるため、禁酒が望ましいです。
- 強化トレーニング期:新しい技術の習得や体力強化に集中する期間は、禁酒が効果的です。アルコールは運動学習や筋肉の適応に悪影響を与える可能性があるためです。
これらの期間中は、水分補給を十分に行い、質の良い睡眠を確保することで、より効果的な身体づくりが可能になります。プロアスリートの場合、チームのトレーナーや栄養士と相談しながら、最適な禁酒期間を設定することをお勧めします。
ボディメイクコンテスト出場者の減量期
ボディビルディングや筋肉美コンテストの出場者にとって、減量期は非常に重要な時期です。この時期のアルコール摂取は、コンディショニングに大きな影響を与える可能性があります。
- アルコールは7kcal/gと高カロリーで、厳密なカロリー管理を必要とする減量期には不適切です
- アルコールには抗利尿ホルモンの分泌を促す作用があり、体内の水分貯留を引き起こします
- 皮下水分の増加により、せっかくの筋肉の定義が見えにくくなってしまいます
- 減量期特有のホルモンバランスの乱れが、アルコールによってさらに悪化する可能性があります
このため、多くのコンテスト出場者は大会8〜12週間前から完全禁酒を実施します。これにより、脂肪燃焼の効率化と筋肉の質を最大限に高めることができます。
トレーニング効果が停滞した場合の一時的な禁酒実験
トレーニングを継続しているにもかかわらず、筋力や体型の改善が停滞している場合があります。そんなとき、一時的な禁酒実験が効果的な打開策となる可能性があります。
- 4〜6週間の完全禁酒期間を設定します
- 実験中は以下の項目を毎日記録します
- 朝の体重と体組成
- トレーニング内容とパフォーマンス
- 睡眠時間と質
- 全体的なエネルギーレベル
- 食事内容と量
この実験を通じて、アルコールが自身のコンディションに与える影響を客観的に評価することができます。ただし、飲酒にはストレス解消や社交といったポジティブな側面もあるため、実験結果を踏まえた上で、自分にとっての適切な飲酒バランスを見つけることが重要です。
まとめ:筋トレする人でも飲酒して問題ない理由
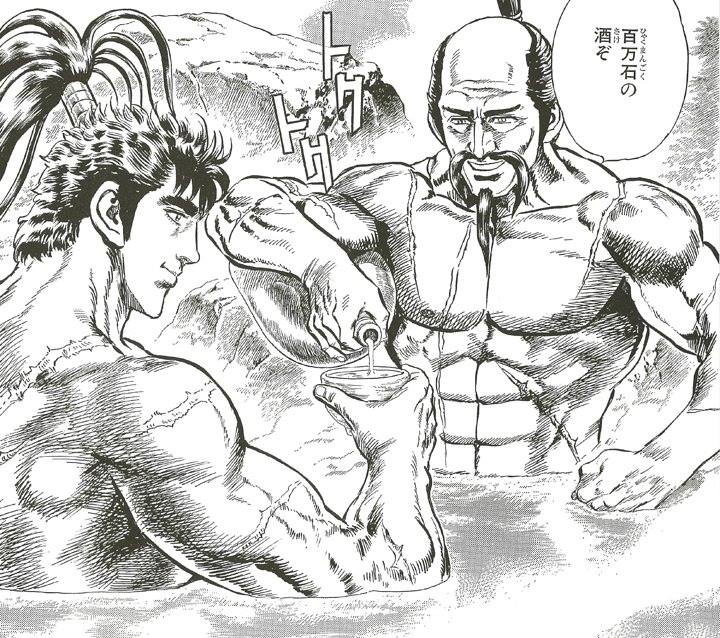
筋トレと飲酒の両立は可能です。適度な飲酒であれば、筋トレの効果を大きく損なうことはありません。重要なのは、セルフコントロールとバランスです。
筋トレの効果が多少減少しても、完全に禁酒するよりも適度に楽しむ方が長続きする可能性が高いでしょう。個人の目標と生活の質のバランスを考慮することが大切です。
ただし、過度の飲酒は避け、トレーニングのタイミングや栄養摂取に注意を払いましょう。また、定期的に自身の体調や目標の進捗をチェックし、必要に応じて飲酒習慣を見直すことをおすすめします。
筋トレと飲酒を上手く両立させることで、健康的で楽しい生活を送ることができるはずです。自分に合った最適なバランスを見つけ、継続的な身体づくりを目指しましょう。
ちなむと、ミルクシスル(シリマリン)サプリおすすめ。
筋トレとお酒を両立したいあなたに、ミルクシスルサプリメントをおすすめします。このハーブには肝臓を保護し、解毒作用を高める効果があり、高タンパク食による肝臓への負担を軽減します。実際に多くのプロボディビルダーが、トレーニング期間中の肝機能サポートとして愛用しています。(高タンパク質食やドーピングへの対処)
ミルクシスルはプロテインとの相性も抜群で、肝臓でのアミノ酸代謝を促進し、筋肉合成をより効率的にサポート。トレーニング後の回復力を高め、パフォーマンス向上につながります。
また週末のお酒も楽しみたい方には、アルコール代謝を促進し肝細胞の再生を助ける効果が魅力です。二日酔いを完全に防ぐわけではありませんが、肝臓へのダメージを軽減し、翌日のトレーニングへの影響を最小限に抑えます。
筋トレの成果を最大化しながら適度なお酒も楽しみたい方は、ぜひミルクシスルを試してみてください。
脚注:
- 適度なアルコール摂取は過負荷誘発性筋肥大およびタンパク質合成を損なわない – PubMed ↩︎
- Alcohol Ingestion Impairs Maximal Post-Exercise Rates of Myofibrillar Protein Synthesis following a Single Bout of Concurrent Training – PMC ↩︎
- Dysregulation of skeletal muscle protein metabolism by alcohol – PMC ↩︎
- The Relationship between Alcohol Consumption and Cortisol Secretion in an Aging Cohort – PMC ↩︎
- Cortisol secretion over the day is increased in heavy drinkers | Nature Reviews Endocrinology ↩︎
- The effects of alcohol on testosterone synthesis in men: a review: Expert Review of Endocrinology & Metabolism: Vol 18, No 2 ↩︎
- Relationship between Alcohol Consumption and Testosterone Deficiency according to Facial Flushes among Middle-Aged and Older Korean Men – PMC ↩︎
- The Diuretic Action of Weak and Strong Alcoholic Beverages in Elderly Men: A Randomized Diet-Controlled Crossover Trial – PMC ↩︎
- Dehydration: physiology, assessment, and performance effects – PubMed ↩︎
- Alcoholic Myopathy: Pathophysiologic Mechanisms and Clinical Implications – PMC ↩︎
- The Genetics of Alcohol Metabolism: Role of Alcohol Dehydrogenase and Aldehyde Dehydrogenase Variants – PMC ↩︎
- Biology, Genetics, and Environment – PMC ↩︎



